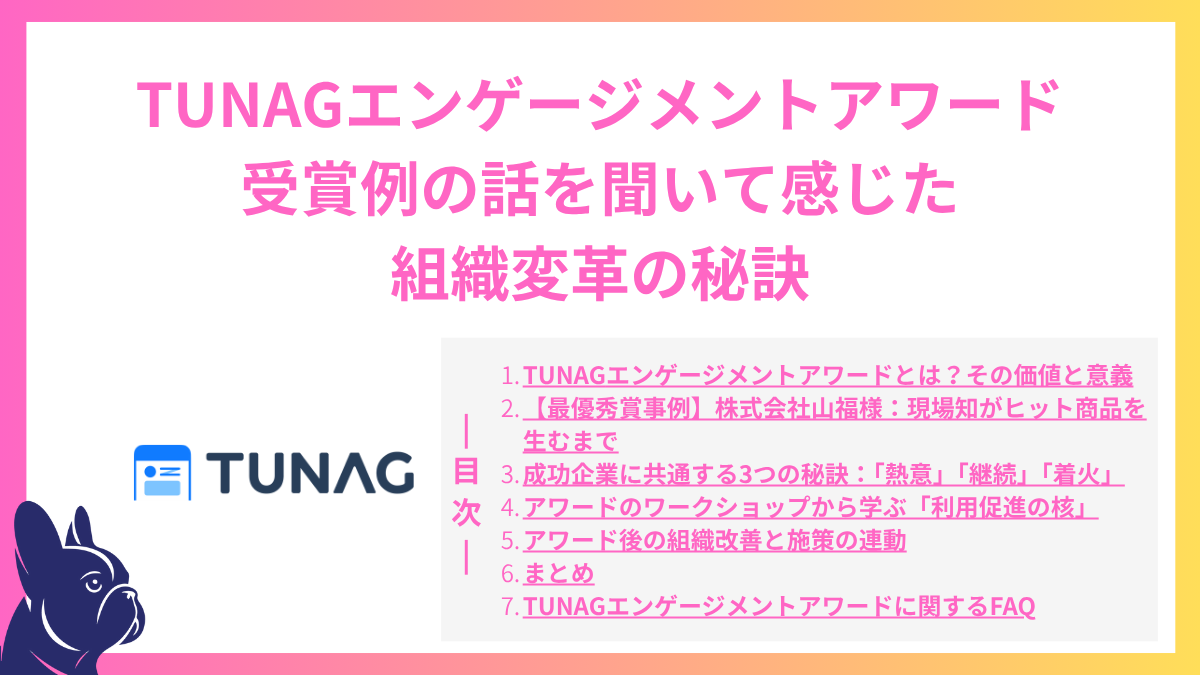- 「TUNAGエンゲージメントアワード」の開催目的と、成功事例から何を学べるか
- 【最優秀賞:株式会社山福様】現場からの情報発信がヒット商品開発に繋がった「嘘のような本当の話」
- アワードの成功企業に共通する「熱意」「継続」「着火」という3つの秘訣
- TUNAGを社内に定着させるために、導入担当者が持つべき「覚悟」とは
- サーベイや制度導入を「成功体験」に変えるアワード後の具体的な運用ノウハウ
エンゲージメント向上ツール「TUNAG(ツナグ)」の導入を検討されている人事・経営層の皆様にとって、「本当に社内で定着し、成果が出るのか?」という疑問は最も大きな懸念事項ではないでしょうか。
多くの企業が「社内SNSを入れてみたものの、一部の部署しか使わない」「サーベイで課題はわかったが、次のアクションが続かない」といった、「ツール導入で終わってしまう」壁に直面します。
こうした中、TUNAGを最大限に活用し、実際に組織変革を実現した企業が一堂に会し、そのノウハウを共有する場が、年に一度開催される「TUNAGエンゲージメントアワード」です。
本記事は、2025年1月に開催された「TUNAGエンゲージメントアワード2024」に参加した私の経験と得た学びを記載します。
単なる導入事例集では語られない、成功企業が持つ「熱意と覚悟」、そして「現場を巻き込む具体的な手法」について、最優秀賞事例の深掘りを含め、徹底解説します。この記事を読めば、貴社がTUNAG導入後の成功イメージを具体的に持つことができるはずです。
TUNAGエンゲージメントアワードとは?その価値と意義
まず、TUNAGエンゲージメントアワードが、一般的な表彰制度とどう違うのかを整理します。
アワードの目的は「成功ノウハウの共有」
アワードは、単に「TUNAGをよく使っている企業を表彰する」ことが目的ではありません。真の目的は、「TUNAGというツールを通じて、従業員エンゲージメント向上と組織変革に成功した企業の具体的なノウハウとプロセスを、広く共有・学習する場」を提供することにあります。
成功事例には、サーベイの活用方法から、社内制度のユニークな設計、現場のデスクレスワーカーを巻き込むための工夫など、導入検討企業が喉から手が出るほど欲しい「生きた知恵」が詰まっています。
TUNAG導入検討者にとって最大のメリット
導入検討者にとって、アワードで共有される事例は「成功の再現性」を確信する材料になります。
- 自社と同じ業種・規模の成功事例が見つかることで、導入後のイメージが明確になる。
- 「なぜその施策を選んだのか」「どんな失敗を乗り越えたのか」という、マニュアルには載らないプロセスを知ることができる。
- TUNAGが持つ複数の機能(サーベイ、サンクスカード、社内報など)をどう組み合わせるべきかのヒントを得られる。

実際に参加をした際には、会社規模ごとに色の違うストラップを配らせ、アワードの交流会にて自社と同規模の企業の担当者と情報交換がしやすい状況でした。こういったところから同じTUNAG導入企業同士で同じ課題を共有したり成功事例をシェア出来たりするのはとても大きなメリットだと感じます。
【最優秀賞事例】株式会社山福様:現場知がヒット商品を生むまで
2025年1月に開催された「TUNAGエンゲージメントアワード2024」の最優秀賞は、業務用食料品を扱う株式会社山福様が受賞されました。その取り組みは、まさに「TUNAGの理想的な活用」と呼べるものであり、多くの企業が抱える「現場と経営の分断」を見事に解消したサクセスストーリーです。
事例の核心:「現場の声」が新たな価値に
山福様の事例で最も驚くべき点は、「TUNAGによって現場からの情報発信がされ、それが直接、ヒット商品の開発につながった」という、一見すると「嘘のようなサクセスストーリー」を現実のものにしたことです。
食料品を扱う同社では、日々製造の現場にいるスタッフこそが、顧客のニーズや市場のトレンド、そして「新たな商品」に対する最も深いインサイトを持っています。しかし、従来の方法では、その貴重な情報が発信される場すらなかったと記憶しています。
山福様はTUNAGの機能を積極的に活用し、現場スタッフが感じたこと、思ったこと、やってみたことなどを気軽に投稿・発信できる仕組みを構築していました。
実現した組織変革
- 情報の民主化: 埋もれていた現場のインサイト(例:「こんな商品をつくってみた」)が、TUNAGを通して全社に可視化されました。
- 商品開発への直結: 投稿されたアイデアやフィードバックを、上役がみつけ、新商品のタネとして活用。実際に、この現場発のアイデアが形となり、大きなヒット商品を生み出すことに成功しました。
- エンゲージメント向上: ここは実際には言及されていたか記憶が曖昧ですが、自分の「ちょっとした気づき」が会社の売上やヒット商品に繋がったことで、現場スタッフの自己肯定感(承認欲求)はあがり、組織全体のエンゲージメントが向上したと思いました。
この事例は、エンゲージメントツールが単なる「仲良しツール」ではなく、「現場の知恵を経営に活かす、戦略的な情報収集・イノベーション創出プラットフォーム」であることを証明しています。
株式会社山福様の詳細な取り組みはこちら(TUNAGアワード2024公式サイト)
成功企業に共通する3つの秘訣:「熱意」「継続」「着火」
アワードに登壇した全ての成功企業から見えてきた、TUNAG活用を成功させるための共通項は、機能や予算といった表面的なものではなく、導入担当者と経営層が持つ「マインドセット」にありました。
秘訣①:導入担当の「熱意」と「覚悟」
最も重要な共通点は、導入担当者、すなわちプロジェクトオーナーの「熱意」と「覚悟」です。
TUNAGの導入は、新しいチャットツールを入れることとは違います。それは「組織文化を変えるプロジェクト」です。文化を変えるには、社員からの反発や無関心といった抵抗勢力に打ち勝つ強い推進力が必要です。
- 「とにかく発信をしなければ始まらない」という強い信念を持つこと。
- 「発信をしつづけなければ変わらない」と、短期的な結果に一喜一憂せず、長期戦を覚悟すること。
成功企業は、この「発信し続ける覚悟」を持ち、自らが最も積極的にTUNAGを使う模範者(ロールモデル)となっていました。
秘訣②:仕組みとしての「継続」
熱意だけでは組織は変わりません。重要なのは、その熱意を「仕組み」に変えて、継続させることです。
アワードの成功企業は、単に「自由に投稿してください」と放置せず、「日報フォーマット」「サンクスカードを送るルール」「月間の投稿テーマ」など、投稿を「義務」ではなく「習慣」にするための具体的な制度設計をTUNAG上で行っていました。
TUNAGの持つ「社内制度の作成・管理機能」を最大限に活用し、属人的な努力に頼らない「組織文化の土台」を築くことが、成功の鍵でした。
秘訣③:上位者と現場への「着火」
成功のサイクルを生み出すには、「熱意が上位者や現場に着火すること」が必要です。
- 経営層への着火: 導入担当者がTUNAGの成果(例:サーベイ結果の改善、活用率)を経営層に定期的に報告し、経営層がTUNAG上で「社長メッセージ」を出す、現場の投稿に「いいね」を押すなどのトップコミットメントを引き出すこと。
- 現場への着火: 現場社員の小さな成功や貢献(例:山福様の「ヒット商品のタネ」)をTUNAG上で可視化し、「自分もやれば誰かの役に立つ」というポジティブな連鎖(承認欲求)を生み出すこと。

担当者が「やらされている」と感じている間は火の元がないので絶対に成功しません。担当者の「暑苦しいくらいの情夏、しつこいくらいの発信・行動の継続」、反発、冷え切った反応など当たり前という覚悟」、これを行い続けながら、決裁者が途中で辞めようと言い出さないくらいに熱意で押し切る。これで「着火」の一歩手前に来たという感覚かなと思います。
アワードのワークショップから学ぶ「利用促進の核」
アワードでは、事例発表だけでなく、TUNAGを社内に利用促進するための重要な考え方を学べるワークショップが開催されました。私もここで、TUNAGを定着させる上での本質的な考え方を再確認しました。
重要な考え方:目的や役割から設計し、何度も立ち戻ること
ワークショップでとても強く感じたのは、「TUNAGはやはりインナーブランディングや社内マーケティングといった文脈のツールと捉えるべきであり、それはマーケティング戦略を立てる考えととても類似している」ということです。ワークショップは、エンゲージメント向上を実現したその先の理想の組織から考え、そこまでのGAPと課題を可視化し、その課題を解決するためにTUNAGはどんな役割で、誰に何を届けるためにんな目標をもって運用すればいいのか。を考える時間でした。これはすべてマーケティング戦略設計と違いません。
つまるところ、結局はその戦略設計を行うこと、日々見直しPDCAを回すこと、これこそが成功の最低条件であると痛感しました。
アワード後の組織改善と施策の連動
アワードで得たノウハウを「点」で終わらせず、「線」として組織改善に繋げるには、TUNAGの各機能を連動させる必要があります。
Step1:成功事例から「自社の課題解決策」を特定
山福様の事例(現場知→商品開発)を参考に、「現場の声をどう吸い上げるか」を自社の課題に照らし合わせます。
- TUNAGでできること:「日報・週報フォーマットのカスタマイズ」「部署横断のアイデア投稿制度の作成」「いいねやコメントに対するポイント付与制度の導入」など。
Step2:施策の実行と定点観測(サーベイ活用)
新しい制度(施策)をTUNAG上で実行したら、必ず効果測定を行います。
- TUNAGでできること:施策実行後、ダッシュボード等でTUNAG上の数字の変化をモニタリング。KPIに対する進捗をモニタリングしながらPDCAを回す。パルスサーベイやエンゲージメントサーベイを実施。「情報共有のしやすさ」「仕事のやりがい」といった項目のスコアが改善しているかを確認します。
Step3:継続的な改善(1on1との連動)
サーベイ結果で特定された「コンディション低下者」や「スコアが悪い部署」に対し、施策を再調整します。
- TUNAGでできること:低下者を自動検知し、1on1支援機能を通じて、上司との質の高い面談を促します。面談を通じて現場の声を再度吸い上げ、次の施策に活かします。

当社のリサーチノウハウである「アンケートを集計・分析して次につながる価値ある情報に変換する」ともリンクします。TUNAGは「サーベイ」と「施策実行」のPDCAを回すための機能が全て揃っている。ツール単体ではなく、このPDCAサイクル全体を回すことが、エンゲージメント経営の本質だと思います。
まとめ
「TUNAGエンゲージメントアワード2024」の成功事例から学べることは、TUNAGの機能的な優位性だけでなく、導入担当者・経営層の「マインドセット」と「継続する仕組み」の重要性です。
- 最優秀賞の山福様の事例は、現場のインサイトを吸い上げることで、エンゲージメント向上が企業の競争力強化(ヒット商品開発)に直結することを証明しました。
- 成功企業の共通点は、「導入担当の熱意」「継続的な仕組み化」「経営層・現場への着火」という3つのマインドセットです。
- アワードのワークショップで学んだように、TUNAGは「伝書鳩」ではなく、「心理的安全性を担保し、双方向性を生み出す場」として運用することが成功の核となります。
TUNAG導入の成功は、ツール選びで決まるのではなく、導入後の運用に「覚悟」と「戦略」を持って取り組むかで決まると言っていいと私は思います。本記事でご紹介した成功企業の秘訣を、貴社の組織変革プロジェクトの参考にしていただければ幸いです。
TUNAGエンゲージメントアワードに関するFAQ
TUNAGのアワード受賞企業は、何か特別な機能を使っているのでしょうか?
いいえ、必ずしも特別な機能を使っているわけではありません。アワード受賞企業の多くは、TUNAGに標準搭載されている「日報・掲示板」「サンクスカード」「社内報」「サーベイ」といった機能を、自社の課題に合わせて「どう組み合わせるか」「どんな制度として運用するか」という点に知恵を絞っています。 最優秀賞の山福様の事例も、既存の「投稿機能」を現場の声の吸い上げという戦略的な用途に振り向けた成功例です。重要なのは「機能」よりも「運用設計」であると言えます。
導入後に全社的な利用を促すための具体的な「最初の一歩」は何でしょうか?
アワードのワークショップでも強調されていたのは、「発言のハードルを極限まで下げること」です。具体的な最初の一歩としては、「業務に直接関係ない、個人的な『人となり』が分かる投稿」から始めるのが非常に有効です。例えば、社長や役員が「週末の趣味」や「最近のランチ」など、親しみやすい内容を投稿し、それに対して現場社員が気軽に「いいね」やコメントをする文化を意図的に作り出します。これにより、「TUNAG=堅苦しい業務連絡の場ではない」という心理的安全性が醸成され、その後の業務に関する投稿にも繋がりやすくなります。
TUNAGの成功事例は、どれくらいの期間で成果が出始めるものですか?
エンゲージメント向上は組織文化の変革を伴うため、短期的な成果(数ヶ月)を期待するのは難しいです。アワード受賞企業も、多くが1年〜3年のスパンで継続的な施策を打ち続けています。ただし、「利用率の向上」や「パルスサーベイによるコンディションの早期把握」といった、ツールの定着に関する効果は、半年以内で明確に現れ始めます。重要なのは、最優秀賞事例の山福様のように、「成果が出るまで継続する」という導入担当者の強い覚悟と、それを可能にする仕組みづくりです。