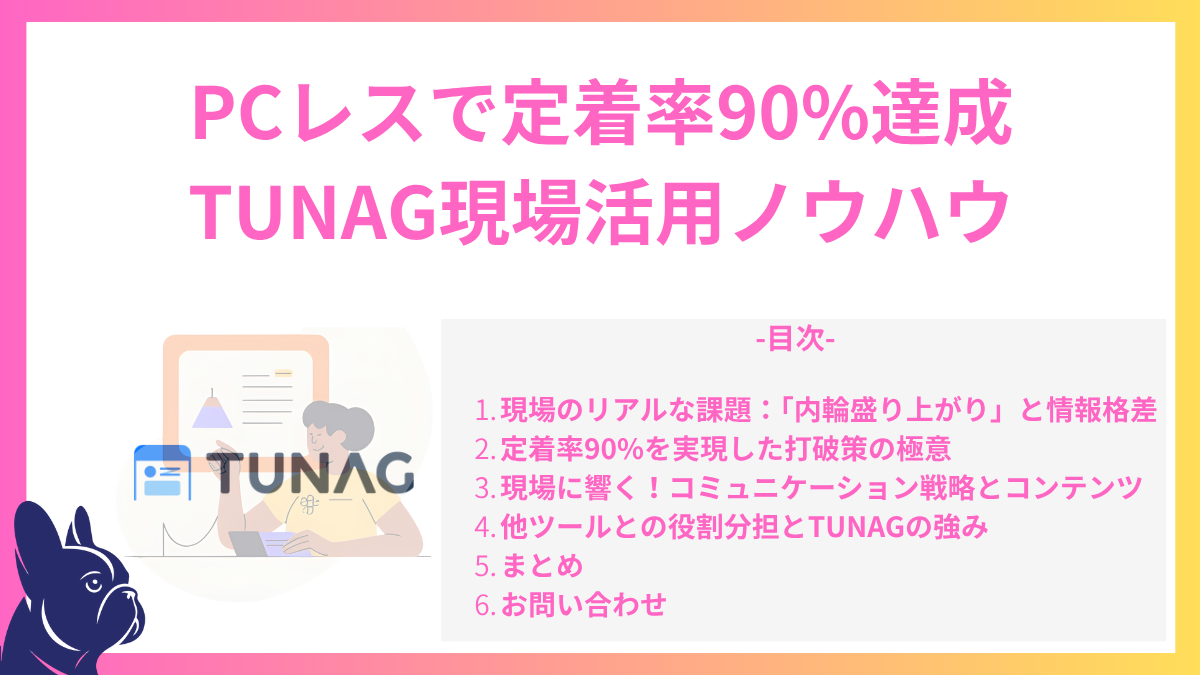社内コミュニケーションの活性化ツールを探している皆さま、「現場社員や派遣社員に情報が届かず、内勤社員との間にコミュニケーション格差が生まれている」という課題を抱えていませんか?
特にPCを持たない環境では、「ツールを入れたら業務が増える」「面倒くさい」という抵抗感が強く、導入しても利用率が上がらずに失敗してしまうケースが後を絶ちません。
私は以前、まさにその課題に直面し、派遣先の技術社員を含む全社員に対し、PCレス環境でログイン率90%を達成させました。
この記事では、現場のIT格差を解消し、社員の自発的な利用を促した「現場特化の運用戦略」を、具体的なノウハウと失敗回避の心構えとともに徹底解説します。
1. 現場のリアルな課題:「内輪盛り上がり」と情報格差
深刻だった「派遣社員」の情報格差
私がTUNAG導入前に最も深刻だと感じていたのは、「派遣先で働く技術社員」の情報格差です。彼らが抱えていたコミュニケーション課題は、単なる情報伝達の遅延以上の問題でした。
- 重要情報が届かない: 大事な社内ルールや、会社全体の動向に関する「郵送物が届かない」「情報が届かない」という不安。
- 内輪盛り上がり感: 本社勤務の内勤社員だけの内輪で情報が盛り上がっていることに対する「疎外感」。
- 問い合わせ先の不明確さ: 就業規則など会社に関する「誰に聞けばいいか分からない」という状態。
この「情報格差」と「疎外感」こそが、エンゲージメント低下、そして離職リスクの増大に直結していました。TUNAG導入の最大の目的は、このIT・情報格差を解消し、「全員が会社の一員」と感じられる基盤を作ることでした。

現場社員の多くは「業務が増える」ことを最も嫌います。彼らの抵抗を打破するには、「強制力」と「自分ごと化できるメリット」を両立させた戦略が必要です。
2. 定着率90%を実現した打破策の極意
現場社員の初期の抵抗(「ログイン方法がわからない」「興味がない」)に対し、私たちは「KPI設計に基づく専門部署による運用」と「利用せざるを得ない導線の確保」を徹底しました。
鉄則1:運用を「プロジェクト」化し、KPIで管理
TUNAGの利用浸透を「プロジェクト」として位置づけ、導入促進の専門部署を設けました。
- KPI設計の3STEP: 活動が惰性にならないよう、段階的なKPIを設定しました。
- STEP 1:ログイン率(まずはアプリを開く習慣)
- STEP 2:閲覧率(必要な情報にたどり着く習慣)
- STEP 3:反応率(いいねやコメントなどの相互コミュニケーション)
鉄則2:給与明細を「キラーコンテンツ」にする強制力
「PCレス環境」の社員に「抵抗なく、日常的に」TUNAGを使ってもらうようになった最大の工夫は、「楽しみとメリット」をTUNAGに集約する強制力でした。
- 具体的な施策: 給与明細の閲覧をTUNAGからしか見れないように導線を制御しました。
- 効果: 給与明細は社員にとって最も重要で楽しみな情報です。これをTUNAGから確認させることで、「ログイン」という面倒な行為が、「給与を確認する」というメリットと完全に結びつき、日常的なログイン習慣が確立されました。
鉄則3:投稿数と投稿時間の徹底管理
利用者のストレスを無くすために、投稿の「量」と「タイミング」を緻密に管理しました。
- 投稿数の管理: 多すぎず少なすぎずを意識し、タイムラインが埋もれるストレスを軽減。
- 投稿時間の変化: あえて朝の通勤時間帯などに投稿するなど、現場社員のライフスタイルに合わせて情報を発信し、通知を見てもらえる確率を高めました。
3. 現場に響く!コミュニケーション戦略とコンテンツ
定着率90%を維持するためには、「本部からの情報」だけでなく、「自分のためになる」「面白い」と感じさせるコンテンツが必要です。
現場社員が評価した「キラーコンテンツ」
現場社員が自発的に投稿や閲覧をするようになったコンテンツは、以下の3つでした。
- 代表メッセージ: 現場の状況を理解した代表のメッセージが、疎外感を解消し、一体感を醸成。
- 新卒の方の発信: 新鮮で作り込まれていない新卒社員のフレッシュな投稿が、既存社員に親近感を与え、閲覧を促しました。
- クーポンや社内イベント関連の通知: 実生活に直結する福利厚生情報や、参加したくなるイベント情報が、楽しみとして評価されました。
「最上部のバナー」でクリックを誘う投稿テクニック
情報発信の際、「現場社員に確実に届き、読んでもらう」ために、投稿の見た目に徹底的にこだわりました。
- 画像戦略: 最上部に細目のバナーを用意し、タイムライン上でバナーが見切れないようにしました。かつ、そのバナーを見ただけで投稿の内容が瞬時にわかり、詳細を見たくなるようにデザインしました。
- 文章のトーン&マナー: 堅苦しい文章は避けるため、「お疲れ様です」などのメール慣習的な挨拶は入れませんでした。マークダウン(太字、リストなど)を使い、起承転結のストーリーを持たせることで、読みやすさと内容の理解度を向上させました。

現場社員は「流し読み」が基本です。画像とタイトルの工夫だけで、「業務に関係のない、でも見たい情報」と瞬時に判断させることが定着の鍵です。
4. 他ツールとの役割分担とTUNAGの強み
チャットツール(Slackなど)との明確な使い分け
現場社員のITリテラシーや利用習慣を混乱させないよう、チャットツールとTUNAGの役割を明確に分けました。
| ツール | 役割 | 現場社員へのルール |
| TUNAG | 全社周知、理念浸透、制度運用、情報ストック | 基本情報(給与明細など)と、長期で残す情報はTUNAGを見る。 |
| Slack / LINE WORKS | 部署単位の即時コミュニケーション | 返信が必要な業務連絡や、部署内のリアルタイムな連携に使う。 |
| メール | 個別宛先指定や返信を要する重要事項 | 宛先を細かくコントロールする場合や、公式な記録が必要な場合。 |
「返信を要する事項はメール優先、それ以外は基本TUNAGが優先」というシンプルなルールを現場に徹底することで、情報の混乱を防ぎました。
現場社員が評価した点と不満点
| 評価された点(メリット) | 不満な点(正直なデメリット) |
| カジュアルな情報連携 | タイムラインで重要情報が埋もれてしまう点 |
| 情報がまとまっている感 | |
| 「とりあえずTUNAG見ればほしい情報あるかも」という安心感 |
現場社員は、TUNAGの「安心感」と「情報が探せる場所」というストック性を高く評価していました。不満点である「情報の埋もれ」は、前述のバナー画像や投稿時間の工夫で運用側がコントロールすべき課題です。
▶ほかにもある特徴はTUNAG公式サイトでチェックしましょう。
5. まとめ
本記事では、PCレス環境の現場社員を主なターゲットとするTUNAGの運用戦略について解説しました。
TUNAGが他のツールと一線を画す点は、スマホアプリの使いやすさと、給与明細連携などの「強い動線制御」ができる運用設計の柔軟性です。
- 成功の鍵: 「給与明細」など、社員が「自分のためになる」と感じる要素をTUNAGに集中させ、「使わざるを得ない習慣」を設計すること。
- 運用の極意: 現場のライフスタイルに合わせた投稿時間や、画像を使った投稿デザインで、社員のストレスを最小限に抑えつつ、情報到達率を高めること。
「PCレス環境」でコミュニケーション活性化に悩む企業にとって、この現場特化のノウハウは非常に強力な武器となります。
わたしがTUNAGと理念動画を通して理念の社内浸透に取り組んだ事例については以下で記載してます。是非ご覧ください。
▶【インナーブランディング 事例】TUNAGで『企業理念』の浸透を実現する運用ノウハウ
【限定無料】元ユーザーによるTUNAG導入・運用個別相談会
あなたの会社が抱える具体的な組織課題をお聞かせください。
前職で培ったTUNAG運用ノウハウに基づき、最適な機能カスタマイズと導入ステップを個別にご提案します。
【相談のメリット】
- 貴社に特化した運用設計フレームワークを無料提供
- デメリットを回避する具体的なフロー設計をアドバイス
- 課題が明確になった高確度のリードとして、TUNAGの公式担当者へスムーズにお繋ぎします。
※ 個別相談をご希望の方は、以下フォームよりお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 現場社員向けのコンテンツ作成は、誰が担当すべきですか?
現場向けのコンテンツ作成は、現場の言語やトーンを理解している担当者が担うべきです。可能であれば、現場経験を持つ広報担当者、または各拠点の若手社員を「アンバサダー」として任命し、彼らに投稿を依頼する運用体制が最も効果的です。本部社員が一方的に作成した堅い文章は、現場社員には届きにくい傾向があります。
Q2. ログイン促進で「給与明細」を使うのは、法的に問題ありませんか?
法的な問題はありませんが、「電子交付」に関する規定に基づき、社員への周知を徹底し、閲覧のための環境や手続きを丁寧にサポートする必要があります。導入初期は特に、ログインや閲覧方法がわからない社員へのサポート体制を、個別相談や動画マニュアルなどで充実させることが重要です。
Q3. 情報が埋もれるという不満に対し、他にできる工夫はありますか?
「情報の埋もれ」はタイムライン型のツールの宿命ですが、以下の運用でカバーできます。
「まとめ機能」の活用: 似たトピックの投稿を一つのまとめ記事として集約し、タイムラインをスッキリさせる。
重要情報固定: 経営方針など、必ず見てほしい情報は「掲示板のトップ固定機能」や「通知の最優先設定」を活用する。
投稿時間の分散: 重要な通知は、あえて現場社員が休憩時間や通勤時間に見やすい時間帯に集中して投稿する。
Q4. 現場社員に「興味がない」と言われた場合、どうモチベーションを高めますか?
「興味がない」という声は、「自分に関係ない」という意味です。モチベーションを高めるには、「業務効率化」または「金銭的メリット」に直結する施策を打つのが最も効果的です。例えば、「現場の知恵やノウハウを共有した社員にポイント付与」や、本記事で紹介した「給与明細導線の設定」など、「見ざるを得ない理由」を提供することが重要です。
Q5. SlackやLINE WORKSからTUNAGへ移行させるメリットは何ですか?
A5. Slackなどのチャットツールは「フロー情報(流れて消える)」に特化していますが、TUNAGは「ストック情報(残る)」と「制度運用」に強みがあります。
TUNAGのメリット: 全社的な理念浸透、評価制度連携、就業規則などの公式情報の集約、そして社員の利用率データを一元管理できる点です。現場社員にとって「会社が公式に提供する情報基盤」として安心感があります。