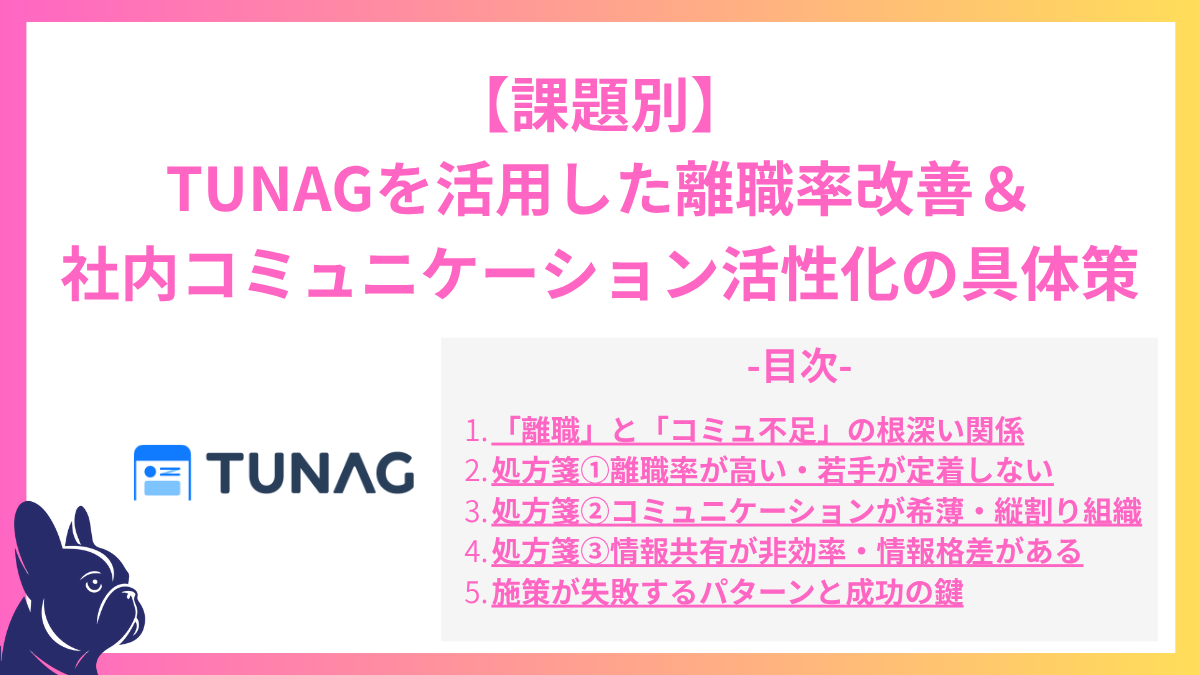- 「離職率の高さ」と「コミュニケーション不足」という2大課題の根本的な関係性
- TUNAGがこれらの課題解決に有効な理由(診断と実行のオールインワン)
- 【離職率改善】パルスサーベイ、1on1支援、サンクスカードを活用した具体的な施策
- 【コミュニケーション活性化】社内報、タイムライン、プロフィール機能を活用した具体的な施策
- TUNAGを導入しても「施策が失敗する」典型的なパターンとその対策
「若手社員の離職が止まらない…」
「部署間の連携が悪く、社内の風通しが最悪だ…」
「経営層の想いが、現場にまったく届いていない…」
こうした「離職率」と「社内コミュニケーション」に関する悩みは、多くの企業担当者様が抱える、非常に深刻な経営課題です。これらの問題は放置しておくと、生産性の低下、採用コストの増大、イノベーションの停滞といった、さらなる悪循環を引き起こします。
表面的な対策(例:懇親会の費用補助、チャットツールの導入)だけでは、根本的な解決に至らないケースも多いのではないでしょうか。
実は、「離職」と「コミュニケーション不足」は、多くの場合、根っこでつながっています。その根本原因こそが「従業員エンゲージメント(会社と従業員の信頼関係)」の低下です。
エンゲージメントツール「TUNAG(ツナグ)」は、このエンゲージメント課題を「診断」し、具体的な施策を「実行」し、組織の仕組みとして「定着」させるために設計されたプラットフォームです。
この記事では、TSRコンサルティングが培ってきた組織戦略の視点から、日本企業が抱えがちな2大組織課題「離職率の改善」と「コミュニケーション活性化」に対して、TUNAGの機能をどう組み合わせてアプローチすべきか、具体的な「処方箋」として徹底解説します。
「離職」と「コミュ不足」の根深い関係
まず、なぜこれら2つの課題が同時に語られることが多いのか、その関係性を整理しましょう。
課題の悪循環サイクル
多くの組織では、以下のような負のスパイラルが発生しています。
- コミュニケーション不足(縦・横)
経営層の想いが伝わらず、部署間の連携もない。 - 心理的安全性の低下と孤立
「誰に相談していいか分からない」「自分の仕事が評価されているか不明」と感じる。 - エンゲージメントの低下
会社への信頼や、仕事へのやりがい(モチベーション)が失われる。 - 生産性の低下と離職
パフォーマンスが上がらず、優秀な人材から見切りをつけて辞めていく。
つまり、コミュニケーションの断絶が「孤立」を生み、エンゲージメントを低下させ、最終的に「離職」という形で現れるのです。離職率だけを問題にしても、その手前にあるコミュニケーション(情報共有や称賛)の問題を解決しなければ、モグラ叩きになってしまいます。
TUNAGが目指す「仕組み」による解決
TUNAGが他のツールと異なるのは、「チャット」や「サーベイ」といった単機能の提供ではなく、これらの課題を生み出す「組織の仕組み」そのものにアプローチする点です。
「離職の兆候を早期発見する仕組み」「称賛が自然と生まれる仕組み」「経営の想いが現場に届く仕組み」——これらを、TUNAGというプラットフォーム上に「社内制度」として設計・実装することで、属人的な努力に頼らない、持続可能な組織改善を目指します。

まさに当社の戦略ノウハウ「WHO-WHATを緻密に行う」ことそのものです。社員(WHO)に対して、会社としての価値(WHAT=働きやすさ、やりがい)をどう届けるか。その「届け方」こそが「仕組み=社内制度」です。TUNAGは、この戦略設計を実行に移すための優れたツールと言えますね。
【処方箋①】離職率が高い・若手が定着しない
離職率、特に新入社員や若手の早期離職は、採用コスト・育成コストの増大に直結する深刻な課題です。これに対し、TUNAGは「予防」と「早期発見」の両面からアプローチします。
Step1:原因の特定(なぜ辞めるのか?)
対策の前に、まずは「なぜ辞めているのか」という原因を客観的に把握する必要があります。勘や思い込みでの施策は失敗します。
<活用機能>
・エンゲージメントサーベイ:年に1〜2回実施する詳細な組織診断。「人間関係」「仕事の負荷」「成長実感」など、組織のどの項目に課題があるかを部署別・年代別などで詳細に分析します。
・パルスサーベイ:週に1回など、高頻度で行う簡単なコンディション調査。「今週のコンディションは?」といった質問で、日々の変化を追います。

当社のリサーチノウハウでも、「意味ある1次情報になるアンケート設計」と「分析して次につながる価値ある情報に変換する」ことを重視しています。サーベイは“取って終わり”が一番の無駄。TUNAGは「どの部署の若手のスコアが低い」といった具体的な分析ができるのが強みです。
Step2:具体策① 早期の不調サインをキャッチ
離職者は、ある日突然辞めるわけではありません。必ずその前に「コンディションの低下」というサインを発しています。それを早期に発見する仕組みです。
<活用機能>
・パルスサーベイ + アラート機能:コンディションが急激に低下した社員や、特定の項目(例:「上司との関係」)が悪い社員をシステムが自動で検知し、上司や人事にアラート(通知)を出します。
・1on1支援機能:アラートが出た社員に対し、上司が1on1ミーティングを設定。面談のアジェンダや過去の記録をTUNAG上で管理し、「ただの雑談」で終わらない、質の高い面談(傾聴とフォロー)を実施します。
Step3:具体策② 心理的安全性の醸成(予防)
社員が「自分はこの組織に受け入れられている」「貢献できている」と感じられる環境(=心理的安全性)を作ることが、離職の根本的な予防策となります。
<活用機能>
・サンクスカード(称賛文化):「〇〇さん、ありがとう」という日々の小さな感謝を、TUNAG上でカード(やポイント)として送り合います。「自分の仕事は誰かの役に立っている」という実感(承認欲求)が、孤立感を防ぎます。
・タイムラインでのリアクション:日報や「#今日の工夫」といった投稿に対し、上司や同僚が「いいね!」やポジティブなコメントを返すことで、見てもらえている安心感を醸成します。
Step4:具体策③ 新入社員を孤立させない仕組み
特に早期離職が多い新入社員(オンボーディング)対策は重要です。
<活用機能>
・日報・週報機能:新入社員に日報を投稿してもらい、メンターや上司、人事だけでなく、他部署の先輩もコメントを書き込めるようにします。組織全体で新人を歓迎する雰囲気を作ります。
・プロフィール機能:趣味や特技、出身地などを登録。既存社員との共通の話題を見つけやすくし、コミュニケーションのきっかけを創出します。
【処方箋②】コミュニケーションが希薄・縦割り組織
「隣の部署が何をやっているか分からない」「経営層と現場の間に深い溝がある」。こうしたコミュニケーション不全は、組織の硬直化と生産性の低下を招きます。
Step1:原因の特定(どこが断絶しているか?)
まずは、「縦(経営と現場)」「横(部署間)」「斜め(他部署の先輩後輩)」の、どこが最も断絶しているのかを把握します。
<活用機能>
・エンゲージメントサーベイ:「経営層への信頼」「部署間の連携」といった項目で、課題のボトルネックを特定します。
・利用状況分析:TUNAGのダッシュボードで、「どの部署とどの部署のサンクスカードのやり取りがないか」「どの層がタイムラインを見ていないか」を分析します。
Step2:具体策① 「縦」のコミュニケーション(経営→現場)
会社がどこに向かっているのか、なぜ今これが必要なのか。経営層の想いを現場に「届く形」で伝えます。
<活用機能>
・社内報(社長メッセージ):社長や役員が、自らの言葉で会社のビジョンや戦略を語る記事を定期的に配信。テキストだけでなく、動画メッセージも有効です。
・理念浸透制度:会社の理念(バリュー)を解説する記事を配信したり、eラーニングでテストを実施したりします。(参考記事:TUNAGは理念浸透になぜ効果的?)

これは当社の「現場と経営層の目線を合わせて組織としてマーケティング戦略を推進する」というノウハウの、まさにインナーブランディング版です。経営の目線(ビジョン)を現場の目線(日々の業務)に翻訳して届けることが、組織を動かす第一歩です。
Step3:具体策② 「横」のコミュニケーション(部署間)
セクショナリズム(縦割り)を解消し、部署間の連携を促します。
<活用機能>
・タイムライン(オープン投稿):日報やプロジェクトの進捗を、あえて全社公開のタイムラインに投稿。「隣の部署の〇〇さんが、今こんな工夫をしている」と知るきっかけになります。
・サンクスカード:部署を超えた協力に対して、積極的にサンクスカードを送る文化を推奨します。「他部署を助けること」が評価される仕組みを作ります。
・社内サークル機能:フットサル部、読書会、ゲーム部など、趣味を通じた「横」のコミュニティを活性化させます。
Step4:具体策③ 「斜め」のコミュニケーション(人となり)
「誰が」「何に詳しいか」が分からないと、コミュニケーションは生まれません。
<活用機能>
・プロフィール機能:業務スキルだけでなく、「趣味」「出身地」「最近ハマっていること」といった「人となり」が分かる項目を充実させます。意外な共通点から会話が生まれることは多いです。
・他己紹介:「私の部署の〇〇さんを紹介します!」といった企画を社内報やタイムラインで実施し、社員の「顔」と「人柄」が見えるようにします。
【処方箋③】情報共有が非効率・情報格差がある
特にPCを持たないデスクレスワーカー(店舗・現場)を多く抱える企業では、情報共有の非効率性がそのままエンゲージメント低下に直結します。
具体策①:情報ポータルとしての一元化
「あのマニュアルはファイルサーバー」「この申請は紙」「重要連絡はメール」といった情報の分散が、非効率の温床です。
<活用機能>
・ドキュメント管理:業務マニュアル、社内規定、各種フォーマットをTUNAGに集約。スマホからいつでも最新版にアクセスできる状態にします。
・お知らせ機能:会社からの公式な通達は、すべてTUNAGの「お知らせ」機能に一本化。「既読確認」機能で、確実に伝わったかを可視化します。
具体策②:デスクレスワーカーへの確実な伝達
現場スタッフに情報を届けるには、彼らのポケットにある「スマホ」に直接アプローチするしかありません。
<活用機能>
・スマホアプリ + プッシュ通知:重要なお知らせや自分宛のチャットが、スマホのロック画面にプッシュ通知で届きます。これにより、情報を見逃すことがなくなります。(参考記事:TUNAGがデスクレスワーカーに強い理由)
具体策③:申請・報告業務のスマホ完結
現場スタッフの負担が大きい、申請・報告業務を効率化します。
<活用機能>
・ワークフロー機能:休暇申請、経費精算、備品発注などをすべてスマホアプリから申請・承認できるようにします。申請のためだけに事務所に戻る、といった無駄を削減します。
・日報・週報機能:現場からの売上報告やヒヤリハット報告なども、スマホから写真付きで簡単に投稿できるようにします。
施策が失敗するパターンと成功の鍵
これだけの「処方箋」があっても、TUNAGの運用に失敗する企業はあります。その多くは、機能の問題ではなく「運用」の問題です。
失敗パターン①:導入が目的化し「課題」が曖昧
「他社がやっているから」「流行っているから」という理由で導入し、「自社のどの課題(WHY)を解決するか」が曖昧なままスタートするケースです。
→ 対策:導入前に「離職率を〇%改善する」「サーベイの〇〇のスコアを上げる」といった、明確な目的(KPI)を設定します。
失敗パターン②:経営層が使わず「人事に丸投げ」
「現場と経営層の目線を合わせる」ためのツールなのに、肝心の経営層がログインすらしないケースです。これでは社員は「人事にやらされている」と感じ、誰も本気で使いません。
→ 対策:社長や役員が、誰よりも本気で使うこと。社内報でビジョンを発信し、現場の投稿に「いいね!」を押す。このトップコミットメントが不可欠です。
失敗パターン③:既存ツールとの「棲み分け」が不明確
「業務連絡はSlack」「情報共有はTeams」「TUNAGは何?」と、社員が混乱するケースです。
→ 対策:「業務連絡・タスク管理=Slack/Teams」「組織文化醸成・制度運用(称賛・サーベイ・社内報)=TUNAG」といった、明確な利用ルール(棲み分け)を定義し、全社に周知徹底します。

ツール導入は、それ自体が一大プロジェクトです。TSRの「戦略を実行する上での関係者との合意形成ノウハウ」や「プロジェクトマネジメントノウハウ」がまさに必要とされる領域です。現場、経営層、人事部、そしてTUNAGのサポート担当者。全員が同じ目的(KPI)に向かって進むための「合意」と「推進体制」を作れるかが、成功の9割を決めると言っても過言ではありません。
まとめ
本記事では、「離職率の改善」と「社内コミュニケーションの活性化」という2大組織課題に対し、TUNAG(ツナグ)がどのように貢献できるかを、具体的な処方箋(機能の組み合わせ)として解説しました。
これらの課題の根本には「エンゲージメントの低下」があり、TUNAGはその「診断(サーベイ)」と「実行(各種機能)」を一つのプラットフォームで完結できる点が最大の強みです。
- 離職率対策:サーベイで原因を特定し、パルスサーベイ+1on1で不調を早期発見。サンクスカードで心理的安全性を醸成する。
- コミュ不足対策:社内報で「縦」の目線を合わせ、タイムラインやサークルで「横」のつながりを作り、プロフィールで「人となり」を可視化する。
ただし、最も重要なのは、TUNAGという「道具」を使って、自社の課題(WHY)に合わせた「制度(HOW)」を設計・運用することです。
ツール導入はゴールではなく、組織変革のスタートラインです。本記事を参考に、自社の課題解決に向けた具体的な第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
課題別活用に関するFAQ
離職率改善だけ、など単一の課題でも導入価値はありますか?
はい、十分に価値はあります。例えば「離職率改善」という課題だけでも、本記事で解説したように「サーベイでの原因特定」「パルスサーベイでの早期発見」「1on1でのフォロー」「サンクスカードでの予防」と、複数の機能を組み合わせて深くアプローチする必要があります。TUNAGはこうした単一課題の「深掘り」にも、複数課題の「網羅」にも対応できる柔軟性を持っています。まずは最優先課題の解決からスモールスタートし、徐々に活用範囲を広げていく企業様も多いです。
すでにSlackやTeamsを使っていますが、コミュニケーション課題が解決しません。
施策を実行した後、効果測定(離職率改善など)はどう行うのですか?
効果測定は非常に重要です。TUNAGでは、定期的な「エンゲージメントサーベイ」のスコア推移で効果を測定するのが一般的です。例えば、「サンクスカード施策」を行った結果、「称賛・承認」や「人間関係」のサーベイスコアが改善したか、といった相関を見ます。また、TUNAGの利用データ(ログイン率、投稿数)と、実際の「離職率」や「業績」といった人事データ(HRデータ)を掛け合わせて分析することも、TUNAGのカスタマーサクセス担当がサポートしてくれます。