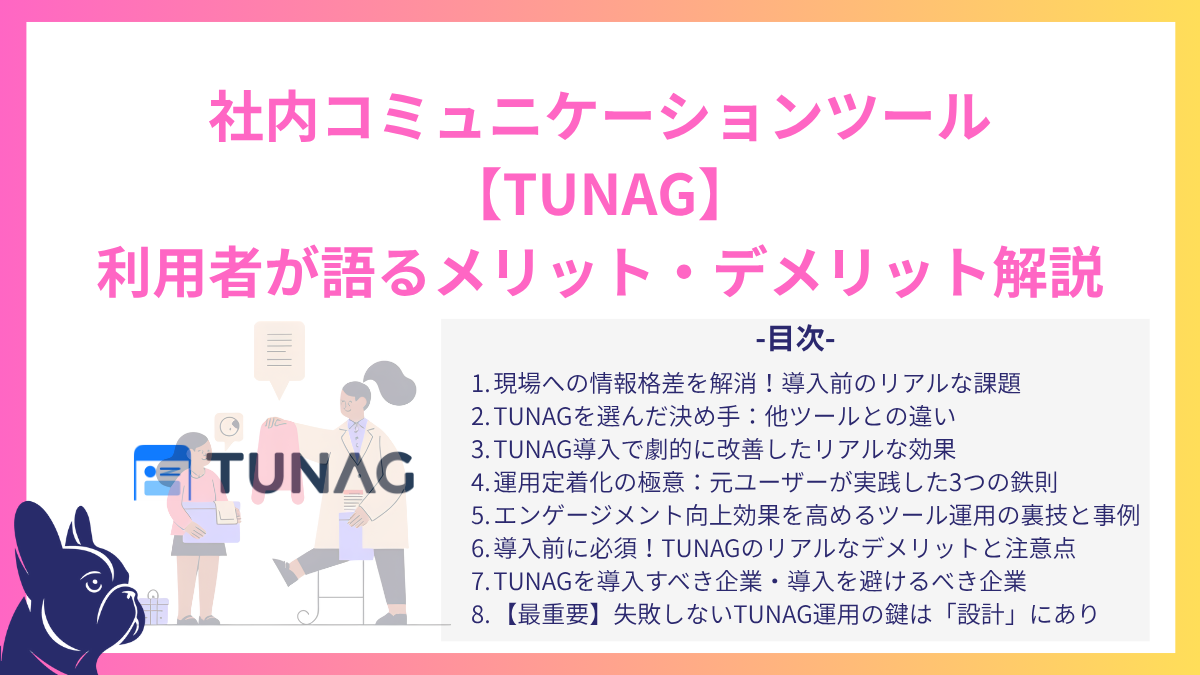組織のエンゲージメント向上を目指し、TUNAG(ツナグ)の導入を検討されている人事・経営者の皆さまへ。
公式サイトや比較サイトで機能や料金を調べても、「本当に自社に定着するのか?」「うちの会社の課題に合うのか?」といった疑問や不安が残るのではないでしょうか。特に、製造業や小売業、飲食業など、PCを持たない現場社員が多い企業では、「ツールを導入しても使われずに終わるのではないか」という懸念は尽きません。
私は以前、まさにその課題に直面し、TUNAGの導入から運用、定着までを自ら担当しました。その経験から、公式サイトには決して載っていない「TUNAGのリアルな強みとデメリット」、そして「ログイン率90%を達成した運用設計の裏側」をすべて公開します。
単なる機能紹介ではなく、生きたノウハウが欲しい—そうお考えであれば、このページを読み終える頃には、あなたの会社がTUNAGを導入すべきか否か、そしてどうすれば成功できるのかが明確になっているはずです。
現場への情報格差を解消!導入前のリアルな課題
深刻な「情報伝達の遅延」問題
私が向き合うべき組織課題は「情報伝達の遅延」でした。なぜなら、会社がPMI期で如何に重要な情報を全社に届けるかが重要な時期で、情報伝達がスムーズに出来ないとそれぞれの立場や拠点などで情報格差が生まれでしまい、大事な時期に同じ目線で会社が前に進まないからです。
- 拠点や部署による情報格差: 本社や経営からの重要事項が、全拠点・全部署・全社員に行き渡るまでに時間がかかり、情報にムラが生じていました。
- 立場による情報格差: 特に自信のPCを持たない派遣先で就業中のエンジニア社員には、社内報やイントラネットの情報が届きにくく、「自分たちは蚊帳の外」という疎外感が出ているケースもありました。
- 理念浸透の遅れ: 社員が議論して熱意を込めて策定された新しい企業理念も、現場まで届かず、「生きた理念」になっていない状態でした。
この状態では、社員の会社への信頼や愛着(エンゲージメント)は高まらず、離職率の抑制にもつながりません。この課題を抜本的に解決するために、私たちは「全社員が日常的にアクセスする情報基盤」としてTUNAGの導入を決めました。

課題解決の決め手は、情報共有の「スピード」と「到達率」でした。特に現場社員に情報が行き渡らない企業は多いですが、ここはTUNAGの強みが最大限に活きるポイントです。
TUNAGを選んだ決め手:他ツールとの違い
スマホアプリと相互の情報連携力
世の中には様々な社内コミュニケーションツールがありますが、私は最終的にTUNAGを選びました。選んだ決め手は、その「現場適用力」と「機能のカスタマイズ性」にありました。
TUNAG導入の決め手となった理由=スマホアプリの手軽さ
TUNAGの社用スマホで手軽に閲覧できるUI/UXは、自社のオフィス以外で勤務する従業員(派遣先で勤務するエンジニア社員や地方拠点の社員、派遣社員やアルバイト)の利用を前提とした設計になっていました。これは、他の多くのツールがPC利用を前提としている中で大きな優位性でした。
- 相互の情報連携が可能な機能: 一方的な情報発信(Web社内報)だけでなく、双方向でのコミュニケーションを促進する機能(サンクスカード、Web日報など)が豊富に標準搭載されている点です。これにより、単なる情報伝達ツールではなく、「エンゲージメント向上ツール」として機能すると確信しました。
- カスタマイズ性の高さ: 企業の課題に合わせて機能のオン/オフや、制度設計を自由に変更できるため、「うちの会社に合ったオリジナルのツール」として育てていける将来性を見出しました。
これなら、社用スマホ×スマホアプリ×リアルタイムな情報発信で情報格差を無くせると思いました。
主要競合ツールとの比較(TUNAGの優位点)
導入時に様々なツールとの比較しましたが、改めて今市場シェアが高い社内SNS比較と比較検討した場合のTUNAGの立ち位置を、元ユーザーの視点で分析しました。
社内SNS(例:Chatwork、Slack)
| 比較項目 | Chatwork / Slackなど | TUNAG |
| 主な目的 | 業務効率化、チャットによる即時連絡 | 組織改善、理念浸透、エンゲージメント向上 |
| 情報伝達 | 流れやすく、重要情報が埋もれやすい | タイムラインで流れる部分はあるが、制度(カテゴリのようなもの)という単位で発信する情報に重要度の傾斜を掛けたり、リンクを固定して確実にストックするなどの伝達の工夫が出来るし、情報の公開範囲も柔軟に設定可能。 |
| 評価制度連携 | 連携が難しい、チャットがメイン | サンクスカードやポイント機能で人事制度との連携が可能 |
| 現場社員の利用 | PC利用がメインになりがち | スマホアプリ特化で現場への定着性が高い |
TUNAGは、チャットツールと異なり、「情報のストック性」と「評価制度との連携」に優れています。
ただ情報連携するだけなら社内SNSでも大丈夫かもしれません。しかし、エンゲージメント向上というもっと大きなGOALを目指したときには重要情報のストック性や情報連携が人事制度や評価制度などと連動してしっかりと社内浸透出来るプラットフォームでないと難しいですので、やはりTUNAGはそういった点で「社内エンゲージメント向上」に特化しているプラットフォームだと感じます。

さらに2025年の4月ごろより、「ポータル機能」が実装され、よりストック型の情報管理もできるし、SNSのようにフロー型で最新の情報が即座に見れるようにもあり、情報伝達はとてもコントロールしやすいようにアップデートされています。
Web社内報(例:他社Web社内報サービス)
| 比較項目 | Web社内報サービス | TUNAG |
| 主な目的 | 一方的な広報・情報共有 | 双方向コミュニケーション、制度運用 |
| カスタマイズ | 記事作成機能がメイン | 掲示板、日報、ワークフローなど20種類以上の機能を組み合わせ可能 |
| 定着化施策 | 記事コンテンツの面白さに依存 | ポイント機能やサンクスカードで、利用そのものを仕組み化できる |
Web社内報は「発信」は強いですが、TUNAGは「発信」に加え「参加」「運用」を可能にするため、「情報が流れるだけ」で終わらない点が大きな強みです。WEB社内報も紙の社内報も行っていましたが、それでだけでは一方通行です。社内のコミュニケーションが活性化することで組織エンゲージメントは向上します。その社内のコミュニケーションが一方通行で良いわけがありません。双方向コミュニケーションを生み出す機能や仕掛けが様々実装されているTUNAGでなければ、組織エンゲージメント向上実現の確率は非常に低かったと感じます。
TUNAG導入で劇的に改善したリアルな効果
導入後、最も「劇的に改善した」と感じたのは、「情報のインフラ化」が実現し、以下の成果が数値として表れたことです。
1. ログイン率が90%に大幅改善
導入後は、週に1回以上ログインする社員の割合が90%以上で安定しました。この高い利用率こそが、TUNAGの最大の価値です。
- 必須情報が8割以上閲覧される状態の維持: 経営方針や安全に関する重要事項など、「必ず見てほしい情報」は、全社員の8割以上が目を通す状態が継続されました。
- 現場の情報格差が解消: PCを持たない現場の社員も、アプリを通じて本部の情報や経営層のメッセージに触れることができ、「会社の一員」としての意識が高まりました。

この「90%」という数字は、情報伝達の成功を意味するだけでなく、社員が自発的に会社にアクセスする習慣が生まれた証拠です。これがエンゲージメント向上の土台です。
2. 「社員で届けたい情報」が回遊する環境へ
単に必須情報を見るだけでなく、社員個人や部署が発信する「プラスアルファの情報」が見られる環境になったことが、エンゲージメント向上に貢献しました。
- 例えば、ある社員が何気ない気づかいをした社員に向けた、「感謝の声」をサンクスカードというTUNAGの機能で届けたことで、その内容が全社に共有され、何気ない行動に対しても感謝、賞賛する賞賛文化醸成のきっかけとなりました。
- これにより、経営層からのトップダウンだけでなく、現場からのボトムアップで情報や理念が浸透する「生きたコミュニケーション」が生まれました。
4半期に一回社員の表彰をする文化がありましたが、あくまでそれは大々的な表彰の場で数字成績を残した営業社員やお客様に直接感謝されたエンジニア社員が中心でした。それがTUNAGで身近に感謝するという行動を全員が見る場で行えることで、ちょっとした小さな成果や貢献に感謝、称賛が生まれました。

このちょっとした小さな成果や貢献に感謝、賞賛が生まれた瞬間こそ、会社として本当に浸透したかった賞賛文化が生まれたきっかけだったかなと思っています。
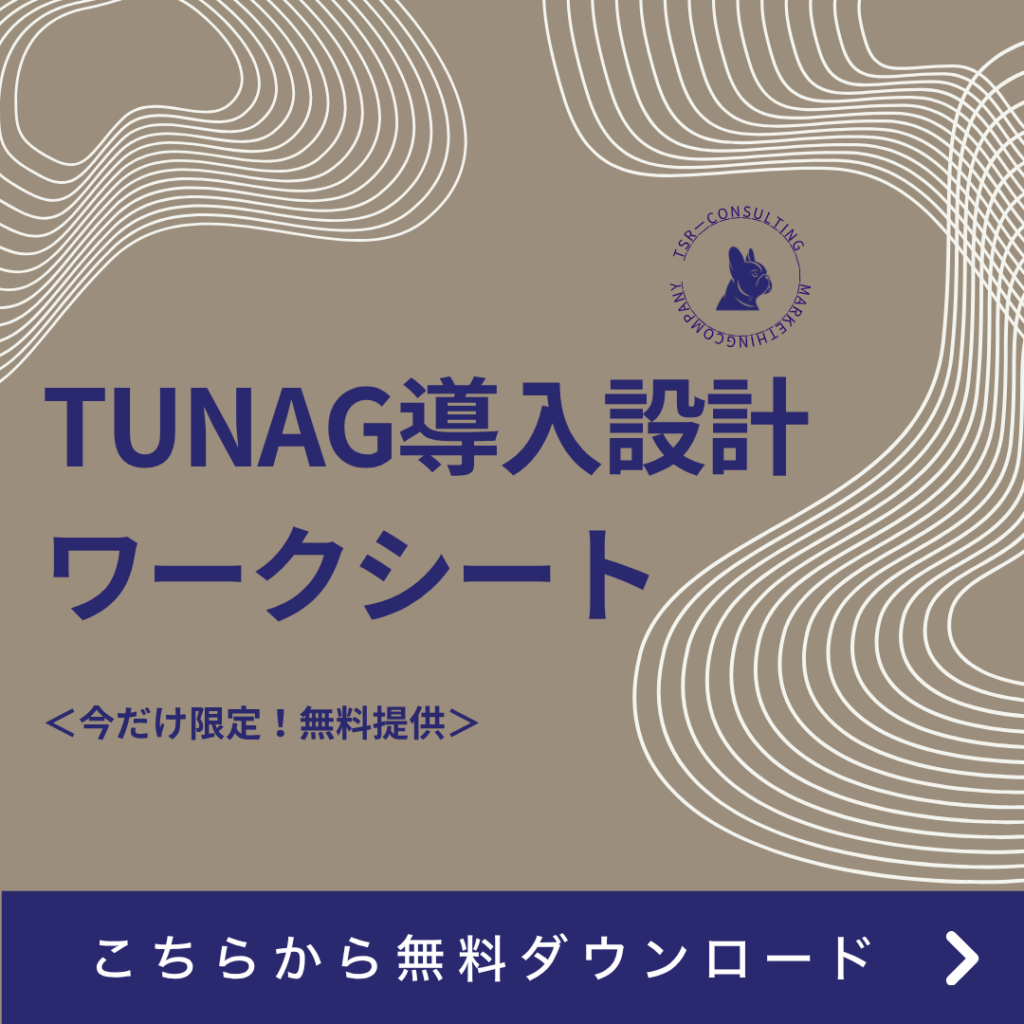
運用定着化の極意:元ユーザーが実践した3つの鉄則
TUNAGは「カスタマイズ性」が高い反面、設計を誤ると「使われないツール」になりかねません。ここでは、私が利用率を維持するために最初に「絶対にやるべき」と決めた3つの鉄則を紹介します。
鉄則1:愛着がわく「ツールの名称」設定
ツールに独自の愛称をつけ、「愛着」や「親しみ」がわくものにすることは、運用初期の重要なステップです。「名称をつけたらどれくらい効果あるの?」とロジカルに期待効果を求める方も出てくると思いますが、ここでロジカルは持ち出すべきではないと私は思います。
それを言い出したら「組織エンゲージメントが向上するとどれだけ売上あがるの?」と同じ議論になり、導入の議論がそこでSTOPしてしまいます。「組織エンゲージメントが下がったから売上が下がった」というファクトの証明が出来ない限り導入の議論が前に進まないことにあり、その証明はこういった話をする段階ではもう証明不可能なケースが多いと思います。ですので、この導入のプロセスでは「楽しく、社員がモチベーション高く活動している未来の姿」を想像し、そのためには愛着もって浸透しているツール名を考えるというビジョンで押し切るコミュニケーションをとるのが良いと思います。
ツール名称決定までのプロセスは公募と投票
名称は可能であれば社内公募するのをおすすめします。社内公募というちょっとした社内のイベントにしてしまうことで、社員の会社に対する興味関心を生み出し、意外な人から素敵な名称が出てくるといった思わぬ発見などもあり組織エンゲージメント向上のきっかけづくりになります。
また公募された名称に対して、投票で決定することを強くおすすめします。公募した名称の中から選ぶのを役員や運営側でおこなってしまうと不平等感がでて決まった名称に愛着が湧きません。それよりも公募して出てきた名称を最低限選定して残った候補をすべて公開し投票させることでいろんなメリットがあります。
ツール名称決定を公募と投票にするメリット
メリット1:ツール名称を覚える
公募は、自分事化して考えさせることが出来るので、応募時も当方時も自分で考えることで記憶に残ります。自分が応募した場合は、その案に決まるかどうか気になりますので、自分の投じた案は何だったかは基本的に忘れません。公募、投票のプロセスを挟むことでより記憶に定着しやすいのがわかると思います。
メリット2:納得感がある
自分も回りも平等に投票し、票数も開示されるのであれば、仮に自身が投じた評にならなかったとしても平等で納得感があります。応募や投票に参加する方々のエンゲージメントを下げるのは会社全体にマイナスです。不平等な決め方だとそのマイナスになるリスクが高まりますので、エンゲージメントが高い方に納得感を持ってもらえるこのプロセスはとても有効であると思います。
メリット3:新たな発見がある
公募することで、応募してくれたかたの才能や完成、得意スキルが見えることもあります。ツール名称だったら名づけのセンスがある人がわかりますし、ツール内で使うロゴを募集したときも素敵なロゴを上手に書けるデザインセンスがある社員を発掘できたりしました。こういった社員のスキルは会社の重要な資源であり、強みになりえます。
TUNAGEngegement Award2024でエンゲージメントオブザイヤーを受賞された株式会社山福様は、若手社員のフレッシュなアイディアという資源がTUNAG上で見つかり、そのアイディアを商品化することでヒット商品を生み出したことが受賞理由ともなっています。
TUNAGEngegement Award2024 株式会社山福様の事例はこちら▶
まとめると、
- 名称を公募し投票で決定:社内で公募出来る状態であれば名称を公募しましょう。社内の1つのイベントとなりますし、皆さんの公募
- 単なる「ツール」ではなく「〇〇(名称)」: 社内では「社内SNS使ってね」ではなく、「〇〇見ておいてね」「〇〇に投稿して」という呼びかけを徹底しました。
- 親しみやすさの醸成: 「ツール」という事務的な響きを払拭し、日々の業務に溶け込みやすくすることで、社員の心理的な抵抗感を減らしました。
といった点が重要であると考えられます。

私がお世話になった方からの受け売りですが、「言葉が人を動かす」と教えていただきました。今振り返ると、社内SNSや社内ツールという名称ではなく○○という自社独自のツール名を作り共通言語にすることで社員が動いたなと思います。
鉄則2:運用初期は「半強制的な利用」を徹底
鉄則1と打って変わって、「抵抗がある」という前提で、食わず嫌いをさせない状況を意図的に作り出すことが、初期定着には重要です。
- 強制的に利用させる設計: 最初の1〜2か月は「使わざるをえない状況」を作り、まずはログイン・閲覧の習慣をつけさせます。
- 専用部署と行動目標の設定: 発信を行う「専用部署」を設け、さらに「最低何件は投稿する」という具体的な行動目標をKPIとして設定しました。これにより、コンテンツの量を担保し、社員がアクセスする理由を強制的に作りました。
未来を見据えて愛着わく名称が出来てもそれだけで利用は進みません。ここは利用促進に徹するというドライな運用がお求められます。如何に社員に「無理矢理感がでないように使わざるを得ない状況」をつくるかが勝負です。

特に一番最初が一番肝心です。最初になーなーで始めてしまうと「そういうものだ」と思われて利用が進みません。最初のインパクトで「重要な楽しい使いやすいツールだから今後も使おう」と思わせる強制的だけど抵抗が少ない導入企画を出来るかが勝負の分かれ目だと思います。
鉄則3:ビジネスと連動させた施策で「負荷をなくす」
利用率が停滞しそうになった時、「社員の負荷(負担)なく、普段の業務になじませる」テコ入れ施策が非常に効果的でした。基本的に利用率は時間と共に徐々に逓減していきます。それを前提において活動をするのは社員ではなく、利用浸透のミッションを担う組織であり、その組織が意図して企画等をしかけていくことが重要です。
ビジネス現場と連動させた施策例
- 営業応援サンクスカードキャンペーン: ちょうど営業成績が低迷していた時期に、「営業を応援する」ことをテーマにサンクスカードの応援メッセージ送付キャンペーンを実施しました。
- 結果: 一番応援された営業社員にはインセンティブを与える企画と連動させた結果、サンクスカードが業務の応援という目的と結びつき、利用率が大きく回復しました。
- スキルシートの更新キャンペーンの実施:期末の社員の評価時期に、評価に直結する自身のスキルシートの更新と提出の導線をTUNAG上からのみに変更しました。
- 結果:評価がお給料に直結するため、強制的にTUNAGにログインしそこからスキルシートを更新sヌルといった行動になり、その流れでTUNAG上の情報を閲覧するといった利用率が向上しました。

ツール定着の失敗の多くは、初期の「食わず嫌い」です。抵抗があるのは当然なので、そこを「運用設計でねじ伏せる」くらいの覚悟が必要です。定着したら、社員が自発的に使い始めます。
エンゲージメント向上効果を高めるツール運用の裏技と事例
ここからは、私が運用を通して発見した、TUNAGの機能を最大限に引き出す「裏技的」な使い方を公開します。
裏技1:サンクスカードは「性善説」ではなく「企画」で回す
サンクスカードは「感謝があれば自然に投稿が増える」という性善説で設計してはいけません。もちろん性善説でうまく企業もいると思いますが、現時点で組織のコミュニケーションに課題があると思っている企業様は避けるべきです。性善説でうまくいくのであれば今もコミュニケーションは比較的うまく行っていると考えるのが妥当ですから、現状課題がある時点で性善説ではうまく行かない組織だと認識して行動するのが成功のためには重要です。
- 裏技: 最初は「企画」や「キャンペーン」で半強制的に実施をさせることが鉄則です。
- 結果事例: 企画と絡めてサンクスカードの送付を促した結果、3ヶ月で何百件ものサンクスカードが飛び交う環境が実現しました。この企画を通じて、社内での「感謝の可視化」が習慣化し、企画終了後も自発的な投稿が続く土壌が作られました。
裏技2:投稿は「新卒・若手」から「作りこみ過ぎない頻度重視」
情報の「質」を求めすぎて投稿頻度が落ちる運用は失敗します。
- 裏技:新卒などの若い方を中心に投稿を促し、「作りこみ過ぎないフレッシュな投稿」を毎日させることを推奨します。
- 効果1: 彼らの新鮮な視点や、等身大の投稿が既存社員に親近感を与え、「自分も投稿してみよう」という利用促進につながります。
- 効果2:新卒のみんなが見ているツールを先輩社員がみていないのは新卒の方からの信頼を失ったり上司に指摘されてマイナスなことも多く、自然と先輩社員が身を引き締めてツールの閲覧を行うようになります。
- テクニック: 投稿の画像は、「横長の細めの形」にしてタイムライン上で画像を見れば何の投稿なのかがわかるように工夫することで、詳細を見たいという動機付けを促します。

TUNAGのダッシュボード機能でどの投稿がどのような実績だったがわかるのでPDCAを回せます。PDCAをしっかり回した結果、投稿時のアイキャッチバナーは横長細めのバナーが最も投稿閲覧率が高いという最適解を導けました。
裏技3:TUNAGのカスタマイズ性を活かした「独自の制度設計」
TUNAGの真価は、自社の課題に合わせた独自制度を構築できる点にあります。
- ポイント制度との連動: 自社独自のポイント制度を制定し、そのポイントをTUNAG上で管理することで、TUNAGの利用そのものにメリットを持たせました。
- 新卒研修への組み込み: 新卒研修が大幅に変わったタイミングで、「新卒専用の投稿制度」をTUNAG内に作り、研修の一環として投稿させました。これもまた、既存社員の利用促進につながる起爆剤となりました。

カスタマイズ性の高さはメリットですが、「何をどう組み合わせるか」が成否を分けます。私の場合はポイント制度と利用促進を紐づけることで、自発的な行動を引き出す仕組みを構築できました。
導入前に必須!TUNAGのリアルなデメリットと注意点
元ユーザーとして、導入前に必ず知っておいていただきたい「正直なデメリット」にも言及します。これらは、導入後の失敗を防ぐための重要な情報です。
1. コメント機能の設定単位に要注意
- デメリット: TUNAGのコメント機能は、制度単位(掲示板やサンクスカードなど)で設定されます。
- 注意点: そのため、コメントを自由にさせることに抵抗のある企業の場合、「誰が」「どこまで」コメントでき、そのコメントを誰が見ると問題になりそうかを導入前に細かく設計し、社内での意思決定を固めておく必要があります。コメント機能の利用を制限したい場合は、運用設計でカバーしましょう。
2. 承認・確認フローの設計は慎重に
- デメリット: 投稿の承認フローにおいて、確認者と承認者を同一の人物で設定した場合、通知が来た際に「確認依頼なのか承認依頼なのか」が分かりづらくなるケースがあります。
- 注意点: 通知が届いた担当者が、「確認でOK」としたタイミングで誤って承認まで進めてしまうリスクがあります。承認をすると投稿され、公開範囲内で公開されてしまうため、翌日まで公開してはいけなかった内容を上司が承認したタイミングで公開されてしまうなどの失敗がありえます。フロー設計時は、承認と確認の役割を明確に分けるか、通知設定を慎重に行う必要があります。
3. スケジュール投稿機能の有無
- デメリット: 投稿にスケジュール投稿機能が搭載されていません(※2025年10月現在)。
- 注意点: 運用担当者が「忙しい時間を避けて通知をONにする」という裏技(前述)を実行する場合、投稿をリアルタイムで行う必要があります。運用負荷を減らすためには、投稿原稿の作成を前倒しで行うなど、運用フローの工夫が求められます。

特にコメント機能はSNSの炎上や風評と同じで、否定的なネガティブコメントが社内拡散されて、いわゆる「ネガティブキャンペーン」になるリスクも含まれますので、リスク管理がとても重要です。
TUNAGを導入すべき企業・導入を避けるべき企業
元ユーザーの経験から、TUNAGの強みが活きる企業と、他のツールを検討すべき企業を明確にお伝えします。
TUNAGの導入を強く推奨する企業
- PCを持たない従業員(現場社員、アルバイト)が多い企業: 小売、飲食、製造、物流、介護など。スマホアプリでの利用に強みがあるため、情報格差の解消に最も効果を発揮します。
- 理念浸透やエンゲージメント向上を最重要課題とする企業: 一方的な広報ではなく、サンクスカードや独自の社内制度を通じて、組織風土を根本から変えたい場合に最適です。
- 組織の課題に合わせて柔軟に施策を変えたい企業: 独自のポイント制度や、部門間の連携など、カスタマイズ性の高さを活かしたい企業。
もちろん他にもFITする企業は様々あると思いますが、私の実体験上はここら辺の企業様にはメリットが強く生きてくるのでオススメです。
他のツールを検討すべき企業
- チャットでのリアルタイムな業務連絡のみが目的の企業: ChatworkやSlackなど、チャット機能に特化したツールのほうが安価で使いやすい場合があります。
- 社員数が極端に少ない企業(30名以下): ツールの導入・運用コストよりも、口頭やメールでのコミュニケーションで十分な場合があります。
- 既に完成されたWeb社内報の機能のみが必要な企業: 記事コンテンツの作成機能に特化した、よりシンプルなWeb社内報サービスが選択肢となる場合もあります。
社員数が少ないけど理念浸透やエンゲージメント向上はしたいというどっちがいいのかわからない場合もあると思いますが、最終最後は費用対効果を含めたメリット・デメリットの天秤で判断していくのが良いと思います。
【最重要】失敗しないTUNAG運用の鍵は「設計」にあり
本記事で触れたように、TUNAGはカスタマイズ性が高いからこそ、「貴社に最適な機能の組み合わせや運用ルール」は個別具体的なものになります。この設計を誤ると、ツールはすぐに使われなくなってしまうという現実があります。
あなたの会社が持つ具体的な組織課題に合わせた最適な導入ステップや、失敗しないための運用設計のフレームワークを知ることが、成功への最短ルートです。
そこで、私がエンゲージメントアワードのワークショップで得た知見と前職での運用ノウハウを凝縮した『TUNAG導入成功への第一歩ワークシート』をご用意しました。このシートを使えば、公式サイトの情報だけでは不安な「導入後の具体的な行動」を段階的に明確化できます。
まずはこのワークシートをダウンロードして、具体的な施策設計を始めてみてください。
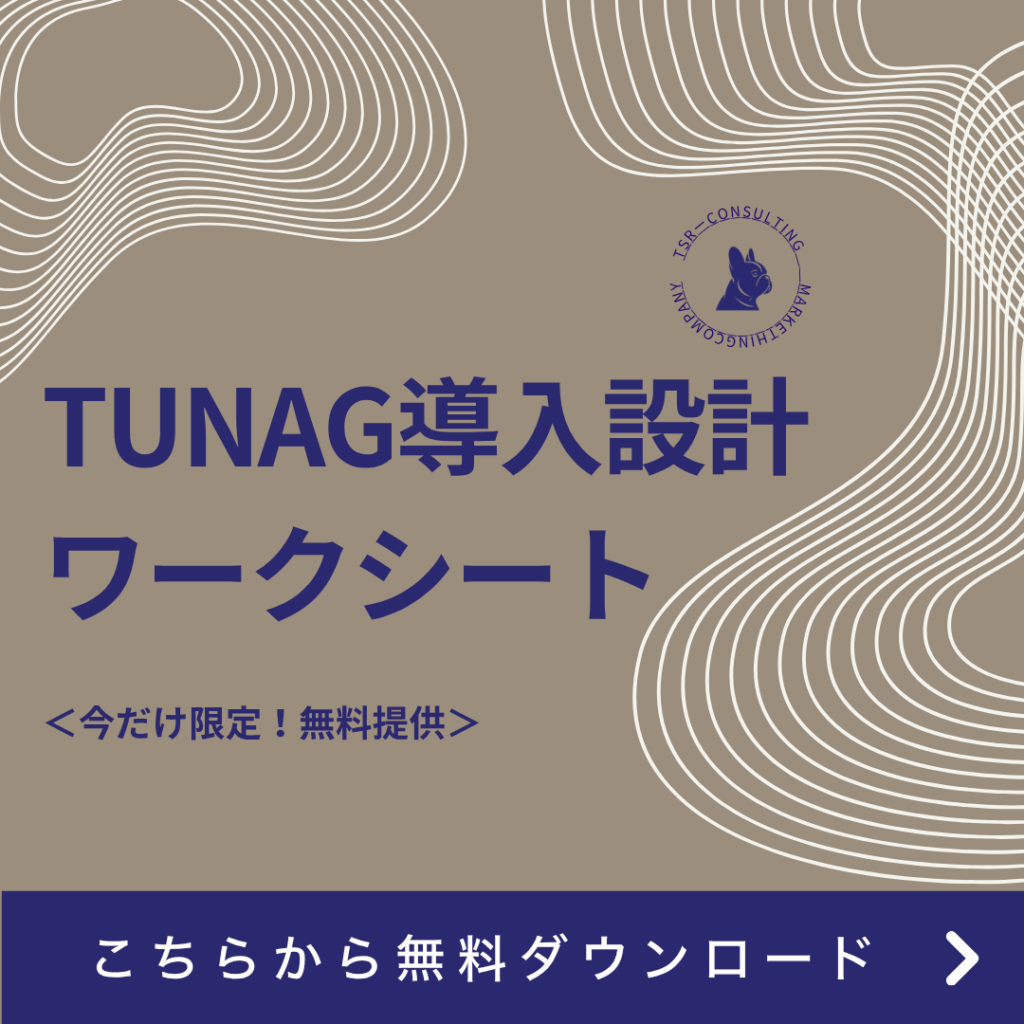
ワークシートだけでは不安な方へ:元ユーザーによる個別アドバイス(無料)
ワークシートを埋めてみて「本当にこの設計で大丈夫か?」「自分の会社の課題に合わせた具体的なアドバイスが欲しい」と不安になった方、まずはお気軽にご相談ください。
導入前でTUNAGからのサポートが得られない状況でいろいろ判断するのは大変だと思います。過去の欧入・運用経験の範囲ではありますが、利用者の先輩として、貴社専用の運用設計ブラッシュアップとTUNAG公式担当者への確実な連携を、責任をもってサポートいたします。
まとめ
本記事では、TUNAGを導入・運用した元ユーザーとしての経験に基づき、公式サイトや比較サイトでは得られないリアルな情報をお届けしました。
TUNAGは、単なる社内SNSやWeb社内報ではなく、「現場の社員も巻き込み、組織エンゲージメント向上を実現する運用型クラウドサービス」です。運用次第で大きな成果につながり、会社を変えるポテンシャルがあるとツールだと言い切れます。
- 最大の強み: スマホアプリによる高い定着率(ログイン率90%)と、豊富な機能のカスタマイズ性。
- 成功の鍵: 初期の「半強制的利用設計」と、「サンクスカードとビジネスを連携させる」といった運用ノウハウ。
しかし、そのカスタマイズ性の高さゆえに、「貴社に最適な運用設計」は個別具体的なものになりますので、設計を誤るとツールはすぐに使われなくなってしまいます。社員全員がTUNAGの利用を通して「繋がる」状態を作り上げる。そんなビジョンをもって導入を検討してみてください。
よくある質問(FAQ)
Q1.TUNAGは導入から定着まで、どれくらいの期間で実現できますか?
導入決定からツールの基盤構築までは最短1〜2ヶ月で可能です。しかし、エンゲージメント向上という成果を出すには、社員がツールを「自発的に使う」状態になることが必要です。私の経験では、運用開始からログイン率90%などの高い定着率を達成するまでには、約3〜6ヶ月間の集中した施策が必要でした。初期の半強制的な利用期間を設け、3ヶ月で習慣化させることが重要です。
Q2.運用担当者が少ないのですが、TUNAGの運用負荷は高いですか?
初期設定や機能のカスタマイズを行う初期段階では、ある程度の工数が必要です。しかし、一度運用が軌道に乗れば、情報伝達や申請業務がTUNAGに集約されるため、トータルでの運用負荷は軽減します。さらに、TUNAGには専任のサポート担当者がつくため、施策のPDCAやアイデア出しは専門家のサポートを受けられます。初期の「仕組み化」にリソースを集中させることが、後の負荷軽減につながります。
Q3.「カスタマイズ性」が高いとのことですが、どのように設計すればいいかわかりません。
まさにこれが、TUNAG導入で失敗する最大の要因です。まず、「最も深刻な組織課題」(例:離職率、情報共有の遅延など)を一つに絞り、その解決に直結する「核となる機能」を設計します。その上で、サンクスカードや日報など、「利用率を高めるための仕掛け」を組み合わせます。私の個別相談では、貴社の業界や従業員数、課題に応じて、この「核となる機能と仕掛けの組み合わせ」を具体的にご提案しています。
Q4.投稿にスケジュール機能がないのは、運用上大きな支障になりますか?
運用担当者の工数管理上はデメリットですが、致命的な支障にはなりません。むしろ、「忙しい時間を避け、リアルタイムで通知をONにする」という裏技で解説したように、投稿タイミングを意識することで、より効果的に情報を届けられるようになります。スケジュール投稿がない場合は、「投稿原稿を事前にまとめて作成し、公開時間を決めておく」という運用フローを定着させることで対応できます。
Q5.弊社は社内での「承認・確認フロー」が厳格ですが、TUNAGで対応できますか?
はい、ワークフロー機能や掲示板の確認ステータス機能で対応可能です。ただし、本記事のデメリットセクションで触れたように、確認者と承認者の役割を明確に分けるなど、「通知の取り違え」が起きないよう、導入時の初期設計でフローを慎重に構築する必要があります。厳格なフローが必要な企業ほど、元ユーザーのアドバイスを受けて導入設計を失敗しないように進めることを強く推奨します。